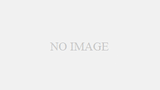お通夜は、故人との最初のお別れの場として、日本の葬儀文化において重要な儀式のひとつです。遺族にとっては突然の準備に追われる時間であり、参列者にとっても厳粛な心持ちで臨むべき場面です。
この記事では、お通夜を執り行う側としての基本的な準備と、当日の流れをわかりやすく解説いたします。初めて喪主や遺族の立場になる方にも安心して臨んでいただけるよう、実務的な視点からご案内いたします。
お通夜とは?
お通夜は、故人と過ごす最後の夜として、亡くなった当日またはその翌日に行われる儀式です。本来は夜通し故人に寄り添うという意味合いがありましたが、現代では1~2時間ほどの略式通夜(半通夜)が主流となっています。
お通夜までに必要な準備
1. 葬儀社との打ち合わせ
故人が亡くなった後、まず葬儀社に連絡し、通夜・葬儀の日程や会場の確保、式の形式(宗教・宗派)について打ち合わせます。
2. 参列者への連絡
親族や親しい知人に電話やメールで通夜の日時・場所を伝えます。近年では葬儀社からの一括連絡サービスを利用するケースもあります。
3. 会場準備・受付体制
香典受付や芳名帳、返礼品などの用意を行います。受付担当や進行補助など、親族内で役割分担をしておくとスムーズです。
4. 遺影写真・遺品・祭壇の準備
遺影写真は葬儀社が加工することもあります。その他、故人が愛用していたものや思い出の品を祭壇に添える準備をします。
お通夜当日の流れ
1. 開式前の準備
参列者の受付を設け、香典を受け取る体制を整えます。遺族は早めに会場入りし、参列者への挨拶や導線の確認を行います。
2. 開式・読経(仏式の場合)
僧侶による読経が行われ、遺族・参列者の焼香が続きます。キリスト教式・神式の場合はそれぞれ異なる進行があります。
3. 焼香
故人を悼む気持ちを表す焼香は、遺族から順に行います。参列者も僧侶や係員の案内に従って焼香します。
4. 喪主・遺族の挨拶(任意)
希望があれば、式の最後に喪主から簡単な挨拶を行います。無理に行う必要はありませんが、感謝を伝える場として適しています。
5. 通夜ぶるまい
式後に軽食をふるまう「通夜ぶるまい」は、故人を偲びながら参列者と語らう時間です。現在では省略されるケースも増えています。
6. お開き・後片付け
参列者を見送り、式場の後片付けや遺族の移動などを行います。葬儀社のスタッフと連携して滞りなく進めましょう。
参列者としてのお通夜マナー
参列者は原則として略式喪服(ダークスーツ・黒のワンピースなど)で出席し、香典はふくさに包んで持参します。
挨拶は「ご愁傷さまです」「心よりお悔やみ申し上げます」など短く丁寧に。遺族の心情に配慮し、過度な会話や詮索は避けましょう。
まとめ
お通夜は、遺族にとっても参列者にとっても、故人と過ごす最後の貴重な時間です。形式にとらわれすぎず、故人への敬意と遺族への思いやりをもって行動することが何より大切です。
初めて喪主や遺族の立場になる方にとっては不安も多いかと思いますが、事前に流れと準備を知っておくだけで、心構えが大きく変わります。この記事が、その支えとなれば幸いです。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
葬儀の流れ・形式クラスター|通夜から法要までの全体像を解説