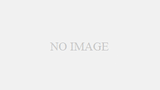スマートフォンが普及した現代において、あらゆる場面で写真や動画を撮影することが一般化しました。しかしながら、葬儀という厳粛な場では、スマホやカメラの使用が慎重に問われる場面でもあります。
「記録として残したい」「遠方の親族に伝えたい」といった理由で撮影を考える方もいれば、「撮影などもってのほか」と感じる方もいるなど、価値観の違いがトラブルの種となることもあります。
本記事では、葬儀におけるスマホやカメラ使用の是非について、基本的なマナーと注意点を参列者・遺族双方の視点から解説いたします。
スマホ・カメラ使用の是非
1. 基本的に撮影は控えるのがマナー
葬儀の場では故人を偲び、静かに祈りを捧げることが目的です。撮影行為が場の空気を壊したり、他の参列者に不快感を与えることもあるため、原則としてスマホやカメラでの撮影は控えるのが礼儀です。
2. 遺族の許可がある場合は例外も
ごくまれに、遺族が記録として祭壇や遺影を撮影したいと希望する場合もあります。このような場合でも、必ず遺族の許可を得た上で行い、周囲に配慮した撮影が必要です。
3. リモート中継・オンライン葬儀の場合
コロナ禍を経て、スマートフォンでのライブ配信やビデオ通話を通じた「オンライン葬儀」も増えています。この場合も、事前に遺族の了承を得て、撮影範囲や音声の管理を徹底することが大切です。
参列者としてのスマホマナー
1. サイレントモードは必須
通夜・告別式・読経中に着信音が鳴ることは大きなマナー違反です。必ず電源を切るか、サイレントモード・機内モードにしておきましょう。
2. 操作音・バイブ音も注意
スマホの操作音やバイブレーションも意外と響くため、完全にオフにするか音が出ない状態で携帯するのが望ましいです。
3. SNS投稿は慎重に
葬儀の写真や動画をSNSに投稿する行為は、遺族や故人のプライバシーを侵害するおそれがあります。たとえ良かれと思っても、勝手に投稿することは避けましょう。
遺族側の対応と配慮
1. 撮影を希望する場合の周知
どうしても記録に残したい場合は、事前に参列者へアナウンスを行い、撮影可否や撮影範囲を明示しておくことでトラブルを防げます。
2. カメラマンを依頼する場合
プロのカメラマンを依頼する場合でも、音を立てない機材や控えめな撮影スタイルが求められます。また、無断撮影されると不快に思う方もいるため、場の空気を壊さない配慮が必要です。
3. オンライン葬儀における注意点
配信時は、写ってはいけない場所や人物に注意し、事前のリハーサルを行うと安心です。また、配信URLの取り扱いにも注意しましょう。
まとめ
葬儀という場において、スマートフォンやカメラの使用には慎重な配慮が必要です。基本的には撮影を控え、どうしても必要な場合は遺族の許可を得た上で、周囲に最大限の敬意を払って行動することが求められます。
現代では便利なツールとしてスマホが浸透していますが、葬儀のような場面では「何をしないか」がマナーの本質と言えるでしょう。この記事を通じて、故人と遺族に寄り添った対応を心がける方が一人でも増えることを願います。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
マナー・服装・所作クラスター|葬儀参列の正しい立ち振る舞い