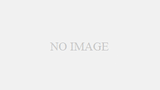葬儀や告別式、火葬を終えたあとに行われる「精進落とし(しょうじんおとし)」。言葉は耳にしたことがあっても、実際にどのような意味を持ち、どのように進めるのか、明確に理解している方は意外と少ないものです。
この記事では、精進落としの意味と目的、当日の流れ、遺族や参列者が押さえておくべきマナーについて、わかりやすく解説いたします。
精進落としとは?
精進落としとは、もともと仏教において喪に服している間に避けていた肉や魚などの「四つ足」を食べることを解禁するという意味合いの儀式です。現代では、葬儀や火葬の終了後、僧侶や参列者を労うための会食として行われるのが一般的です。
いわば、葬儀の締めくくりであり、労をねぎらう「お清めの食事」としての位置づけがあります。
精進落としの流れ
1. 火葬場から戻ったあとの集合
火葬を終えた後、遺骨を収めた骨壺を持って会場(斎場、寺院、もしくは会食場)に戻ります。ここで、参列者や僧侶を迎え、精進落としの準備を整えます。
2. 挨拶・献杯
喪主または施主が挨拶を行い、故人への想いと参列者への感謝の意を伝えます。続いて、代表者による「献杯(けんぱい)」で会が始まります。これは故人を偲ぶ乾杯の儀であり、「乾杯」と言い換えることは避けましょう。
3. 会食
基本的には和食が中心で、故人の好物を用意することもあります。食事中は会話も可能ですが、静かに故人を偲ぶ雰囲気を保つことが望まれます。
4. 閉会の挨拶
最後に喪主または代表者から改めて参列のお礼を述べ、会の終了を告げます。引き出物や返礼品を渡すタイミングもこのときが一般的です。
誰を招くべき?
精進落としには、火葬に同行した親族・親しい友人・僧侶が招かれることが一般的です。すべての葬儀参列者を招く必要はなく、家族や近しい人々に絞ることで、より落ち着いた雰囲気で行えます。
会食を行わない場合の対応
近年では感染症対策や家庭の事情により、精進落としを省略するケースも増えています。その場合は、持ち帰り用の弁当や引き出物を用意し、感謝の気持ちを形として伝える方法が一般的です。
精進落としと「初七日法要」の関係
地域や宗派によっては、火葬後すぐに「繰り上げ初七日法要」を行い、その後に精進落としを実施するという流れもあります。この場合、法要の場としての厳かさも求められるため、服装や言葉遣いにはより一層の配慮が必要です。
服装とマナーのポイント
- 服装:遺族・参列者ともに喪服のままで参加するのが通例
- 言葉遣い:「ご愁傷さまでした」「本日はありがとうございました」といった丁寧な表現を
- 態度:飲み過ぎや騒がしい会話は避け、控えめに振る舞う
まとめ
精進落としは、葬儀を終えた安堵のひとときであり、故人を偲びつつ、関係者に労いの気持ちを伝える大切な儀式です。
形式にとらわれすぎずとも、感謝と礼節をもって臨むことで、心のこもった「締めくくりの場」となります。参列者の立場であっても、静かな思いやりをもって行動することが、故人への何よりの供養となるでしょう。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
葬儀の流れ・形式クラスター|通夜から法要までの全体像を解説