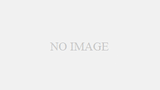ご家族が年金を受給している状態で亡くなった場合、遺族は速やかに年金に関する各種手続きを行う必要があります。放置してしまうと不正受給扱いとなるリスクもあるため、早めの対応が求められます。
しかし、実際にどこに、いつ、何を届ければよいのか分かりにくいもの。本記事では、年金受給者が亡くなった際に必要な手続きを一覧形式で整理し、わかりやすく解説いたします。
まず行うべきこと:「受給停止」の手続き
国民年金・厚生年金受給者の場合
日本年金機構へ「受給権者死亡届(報告書)」を提出します。
- 提出先:最寄りの年金事務所または郵送
- 提出期限:原則として死亡から14日以内
- 必要書類:
- 年金証書
- 死亡診断書または死亡届の写し
- 受給権者死亡届(年金事務所でもらえます)
共済年金受給者の場合
各共済組合(国家公務員共済・地方公務員共済など)に連絡し、所定の書式で手続きを行います。
死亡後に年金が振り込まれた場合
死亡した月の年金は原則「受給権消滅」扱いとなります。つまり、その月分が振り込まれていても受け取ることはできません。
そのため、振り込まれた年金は金融機関により自動的に返金処理される場合があります。
未支給年金の請求手続き
亡くなった方が受け取るはずだった年金(たとえば前月分など)を、遺族が「未支給年金」として受け取ることができます。
請求できる人
- 同居していた配偶者
- 同居していた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
必要書類
- 未支給年金・死亡届に関する請求書
- 受取人の身分証明書
- 振込先の通帳コピー
- 住民票の除票(故人のもの)
- 続柄が確認できる戸籍謄本
提出期限
死亡の翌日から5年以内に請求する必要があります。
遺族年金の申請(条件あり)
故人が受給していた年金が厚生年金や共済年金だった場合、一定の条件を満たすことで遺族が遺族年金を受け取れる場合があります。
代表的な種類
- 遺族基礎年金:18歳未満の子どもがいる配偶者など
- 遺族厚生年金:一定の年齢や扶養条件を満たす配偶者
申請には詳細な審査があり、年金事務所での相談が推奨されます。
手続きをスムーズに進めるためのポイント
- 早めに年金事務所へ連絡し、書類一式を取り寄せておく
- 郵送ではなく、窓口での相談・提出の方が確実
- 複数の手続きがあるためチェックリストを作成すると便利
まとめ
年金受給者が亡くなった場合には、受給停止・未支給年金の請求・遺族年金の確認と、いくつかの重要な手続きが必要になります。提出期限を過ぎると権利を失う可能性もあるため、迅速かつ確実な対応が求められます。
悲しみの中での手続きは大変かもしれませんが、事前に流れや必要書類を把握しておくことで、心の負担を減らすことができます。年金事務所や葬儀社のサポートも活用しながら、正しく丁寧に手続きを進めていきましょう。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
葬儀後の手続きクラスター|相続・名義変更・行政手続きを網羅