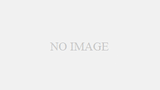葬儀や法要の際、僧侶に渡す謝礼として欠かせないのが「お布施」です。しかし、日常生活で関わる機会が少ないために、「どれくらいの金額を包めばよいのか」「どうやって渡すべきなのか」と迷われる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、お布施の意味から相場、そして包み方や渡し方のマナーまで、基本的な知識をわかりやすく解説いたします。故人を丁寧に見送るためにも、心を込めた正しいマナーで対応できるようにしておきましょう。
お布施とは?
お布施とは、葬儀や法要など仏事の際に、僧侶へ感謝の気持ちとして渡す謝礼のことです。本来は金銭に限らず、物品などを含めた「施し」を意味する仏教用語ですが、現代では金銭による謝礼が一般的となっています。
注意すべきは、お布施は「サービスの対価」ではなく、あくまでも布施行(ふせぎょう)=善行としての意味を持つということ。そのため、形式だけでなく、心を込めて包むことが大切です。
お布施の相場
お布施の金額には明確な決まりはありませんが、地域や宗派、寺院との関係性、そして儀式の内容によってある程度の目安があります。
葬儀・告別式の場合
- 僧侶1名:20万円〜50万円程度
- 複数の僧侶を招く場合:50万円以上になることも
初七日・四十九日法要など
- 3万円〜5万円程度
年忌法要
- 1万円〜3万円程度
これらに加えて、「お車代」や「御膳料」など、別途渡すこともあります。
お布施の包み方マナー
1. 包み紙・のし袋の選び方
- 白無地の封筒または奉書紙を使用します。
- コンビニなどで販売されている「お布施用」ののし袋でも可。
2. 表書きの書き方
- 表書き:「御布施」「御礼」など(黒墨で書く)
- 裏面:施主の氏名と住所を記載
3. お札の向き
新札でも古札でも構いませんが、シワの少ない綺麗なお札を選び、表面(人物側)を上にして入れます。
4. お車代・御膳料の分け方
「お布施」とは別に、遠方から来てもらった場合の交通費や、会食ができない場合の代替として以下のように包みます:
- お車代:5,000円〜10,000円程度(のし袋の表書きは「御車代」)
- 御膳料:5,000円〜10,000円程度(のし袋の表書きは「御膳料」)
お布施の渡し方
- 渡すタイミング:儀式の前後。僧侶の到着時または帰り際が一般的
- 渡す場所:控室や玄関など、人目を避けた場所が望ましい
- 渡し方:袱紗(ふくさ)に包み、両手で丁寧に渡す
- 言葉:「本日はどうぞよろしくお願いいたします」「ささやかではございますが、どうぞお納めください」など丁寧な言葉を添える
まとめ
お布施は単なる金銭のやりとりではなく、故人を敬い、僧侶への感謝を表す心のこもった行為です。そのため、金額の大小よりも、正しいマナーと誠意ある対応が何より大切です。
この記事を参考に、包み方や渡し方をしっかり押さえて、安心して儀式に臨めるようご準備ください。心を尽くすその姿勢こそが、故人への最大の供養となることでしょう。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
香典・お布施・返礼クラスター|金銭マナーと贈答作法の完全ガイド