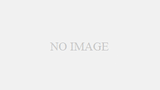故人が亡くなった直後から通夜までの間には、喪主や遺族が行うべき儀式や手続き、準備が多くあります。その第一歩となるのが「枕経(まくらぎょう)」です。
突然の訃報に動揺しながらも、適切な段取りで儀式を進めていくことは、故人に対する最大の敬意でもあります。
本記事では、枕経から通夜を迎えるまでの流れについて、儀式的な意味合いから実務的な準備までをわかりやすくご紹介いたします。
枕経とは何か?
枕経とは、故人が亡くなった直後、遺体を安置した場所(主に自宅や病院、葬儀社の安置室など)で僧侶が読経を行う仏教儀式です。
死後すぐに行う最初の供養であり、故人の魂が迷わず成仏するよう祈るとともに、遺族が精神的な区切りをつける意味合いもあります。
枕経の主な内容:
- 僧侶による読経(約15〜30分)
- 遺族の焼香
- 僧侶から今後の流れの説明
枕経の際には喪服を着る必要はありませんが、黒や落ち着いた色合いの服装を選ぶのが無難です。
枕経後に行う段取り
1. 葬儀社への連絡と搬送手配
枕経後、または前後して葬儀社に連絡を入れ、遺体の搬送・安置・通夜や葬儀のスケジュールについて打ち合わせを行います。迅速かつ丁寧な対応が求められます。
2. 喪主・施主の決定
誰が喪主(遺族代表)となるかを決め、葬儀全体の連絡窓口を一本化します。場合によっては施主(法要の主催者)も別に立てることがあります。
3. 安置と枕飾りの準備
遺体を安置する部屋には、白木の枕飾り(ろうそく・線香・鈴など)を設け、線香を絶やさず供養します。葬儀社が準備してくれることが一般的です。
4. 死亡届・火葬許可証の取得
医師から発行される死亡診断書を基に、市区町村の役所で死亡届を提出し、火葬許可証を受け取ります。通常は葬儀社が代行してくれます。
通夜の準備に向けて
1. 日程と会場の決定
通夜・葬儀の日時、式場、宗教形式(仏教・神道・キリスト教など)を決め、僧侶や神父などの手配も行います。
2. 参列者への連絡
親族、友人、会社関係者などに通夜の日時と場所を伝えます。最近ではLINEやメールなども併用されていますが、年配の方には電話が丁寧です。
3. 香典返しや通夜ぶるまいの準備
返礼品や通夜ぶるまい(軽食)の手配もこのタイミングで進めます。参列者の人数を想定して、多めに準備するのが一般的です。
4. 遺影写真と祭壇の手配
故人の写真から遺影を作成し、葬儀社が祭壇を用意します。遺品や愛用品を飾ることも可能です。
遺族が心がけるべきこと
突然の悲しみの中でも、遺族は多くの判断を迫られます。しかし、すべてを完璧にこなす必要はありません。葬儀社や親族のサポートを得ながら、一つひとつ丁寧に対応していけば十分です。
また、通夜までの間、できるだけ静かに過ごし、故人との時間を大切にすることも、心の整理につながります。
まとめ
枕経から通夜までは、故人との最初の別れの準備期間でもあり、遺族の心の準備期間でもあります。形式的な儀式の裏には、深い意味と祈りが込められているのです。
段取りや手続きに追われる中でも、故人を想う気持ちを大切にしながら、落ち着いて準備を進めてまいりましょう。葬儀社や僧侶の力を借りつつ、心のこもった通夜を迎えることが、何よりの供養となります。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
葬儀の流れ・形式クラスター|通夜から法要までの全体像を解説