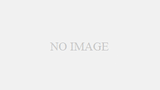人が亡くなった直後、ご遺体の枕元に供物や仏具を並べる「枕飾り(まくらかざり)」という習慣をご存じでしょうか。これは、故人の魂を慰め、旅立ちを見守るための大切な儀式のひとつです。
しかし、枕飾りは宗派によってその形式や配置、意味合いに違いがあり、遺族として正しく理解しておくことが求められます。
本記事では、枕飾りの基本的な意味や準備方法、そして仏教各宗派における違いを丁寧に解説してまいります。
枕飾りとは?
枕飾りとは、故人が亡くなった後、納棺までの間にご遺体の枕元に設置する供養の祭壇のことです。死後すぐの時間は「枕経」などの仏事を行うまでの準備期間であり、枕飾りは故人の霊を落ち着かせるための空間でもあります。
主な目的
- 故人の魂を慰める
- 枕経を行う場所を整える
- 遺族や親族が手を合わせて祈る場所を設ける
納棺までの短期間ではありますが、心を込めて整えることが大切です。
枕飾りの基本的な構成
地域や葬儀社によって細かな違いはあるものの、一般的な枕飾りには以下のようなものが含まれます:
- 香炉:線香を焚くための器。香煙で霊を清める
- 燭台:ロウソク立て。仏の智慧の象徴とされる
- 花立:一輪挿しの供花。白い菊やカーネーションが主流
- 鈴(りん):読経時に鳴らす仏具(宗派によっては用いない)
- 茶湯:湯呑に注いだお茶。故人への最後のもてなし
- 枕団子:故人が旅立つための糧とされる(地域差あり)
宗派による枕飾りの違い
浄土宗・浄土真宗
- 浄土宗では伝統的な枕飾りを行い、枕経の読経が重視されます
- 浄土真宗では、「死後の成仏はすでに阿弥陀如来により約束されている」との教えから、枕経や枕団子は省略される場合がある
曹洞宗・臨済宗(禅宗)
- 枕経は重視されるが、形式はやや簡素
- 枕団子や鈴は使わないことが多い
日蓮宗
- 枕経は重要視され、読経の際には木鉦(もくしょう)や太鼓が使われる
- 法華経の教義に則り、特定の読経文(お題目)を唱える
真言宗
- 密教形式に基づくため、独特の仏具や儀礼が加わる
- 枕経には真言を唱え、鈴や独自の数珠を使う場合も
このように、宗派ごとに枕飾りの内容や意味合いに微妙な違いがあり、葬儀社や菩提寺に事前確認をすることが望まれます。
準備と注意点
- 宗派・地域の慣習を尊重:迷ったら葬儀社や寺院に相談を
- 清潔感のある設置:布や供物の配置は整然と
- 線香やロウソクの火の管理:常時つけておく場合は特に注意
まとめ
枕飾りは、故人がこの世を旅立つにあたって、最初に設けられる祈りの場です。たとえ短時間でも、心を込めて整えることで、その後の葬送の儀式に丁寧さが宿ります。
宗派によって細かな作法の違いはあるものの、故人への敬意と祈りの気持ちは共通。家族で協力しながら、感謝を込めて準備してまいりましょう。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
香典・お布施・返礼クラスター|金銭マナーと贈答作法の完全ガイド