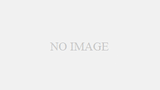葬儀に参列する際、黒い喪服や香典袋とともに用意しておきたいのが数珠(じゅず)です。数珠は、仏教における祈りの道具として古くから用いられており、葬儀や法要の場でも重要な意味を持ちます。
しかし、いざ準備しようと思っても、「どんな数珠を選べばいいのか?」「宗派によって違いがあるのか?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、数珠の基本構造と種類、宗派ごとの使い方やマナー、さらには選び方のポイントまでをわかりやすく解説いたします。
数珠とは?
数珠は仏教の修行道具のひとつで、念仏や真言を唱える際に、回数を数えるための道具として使われてきました。現在では、故人への祈りの気持ちを表すものとして、葬儀や法要などの仏事で使用されます。
数珠の種類
1. 略式数珠(片手数珠)
どの宗派でも使える一般用の数珠。男女で珠のサイズや色に違いがあります。
- 男性用:珠が大きめ、黒や茶系の落ち着いた色
- 女性用:珠が小さめ、藤色やピンク、水晶など柔らかい色も可
2. 本式数珠(正式数珠)
宗派ごとに構造や珠の数が決まっている正式な数珠です。宗派への帰属意識が強い方や法事で僧侶に近い立場にある方は本式を使う場合があります。
宗派ごとの本式数珠の違いと使い方
浄土宗・天台宗・臨済宗・曹洞宗(禅宗)
- 珠数:108珠やそれに準じた数
- 持ち方:左手にかけ、合掌時に手にかける
- 特徴:比較的略式数珠でも問題なく使用可能
浄土真宗本願寺派(西)・大谷派(東)
- 珠数:二連の本式数珠が基本
- 持ち方:房を下にして両手で包むように持つ
- 特徴:焼香の際も合掌ではなく包み持ちする
日蓮宗
- 珠数:主珠108個+親珠2個
- 持ち方:合掌した手に数珠をかける
- 特徴:「振り数珠」と呼ばれる動作あり(唱題時に珠を回す)
真言宗
- 珠数:本連数珠、二連構造
- 持ち方:合掌して数珠をかける
- 特徴:念珠の構造が複雑で、正式な作法が重視される
数珠を使う際の基本マナー
- 合掌時:両手にかける、または左手に持ったまま合掌
- 持ち歩くとき:袱紗(ふくさ)や専用の数珠袋に入れる
- 落とした場合:不吉とされるため丁寧に拾い、祈りを込めて扱う
数珠を選ぶときのポイント
- 宗派が決まっていない場合:略式数珠が無難
- 男女の違いに注意:珠のサイズやデザインが異なる
- 素材:黒檀・白檀・水晶・アクリルなど。法事や服装に合わせて選ぶ
まとめ
数珠は単なる小物ではなく、故人への祈りを形にする大切な仏具です。宗派によって形や持ち方に違いがあるとはいえ、共通して大切なのは、数珠を通じて心を込めて故人を偲ぶ姿勢にあります。
ご自身の宗派に合わせた数珠を用意することはもちろん、迷う場合は略式数珠を選び、丁寧に扱うことを心がけましょう。正しい知識とマナーを身につけることで、葬儀や法要の場でも安心して対応できるようになります。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
香典・お布施・返礼クラスター|金銭マナーと贈答作法の完全ガイド