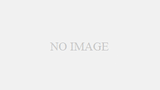葬儀は突然の出来事であることが多く、費用の準備が整っていないまま直面するケースも少なくありません。そんなとき、少しでも経済的な負担を軽減する手段として注目したいのが公的な補助金・助成金制度です。
国や自治体が提供しているこれらの制度を上手に活用すれば、葬儀費用の一部をカバーできる可能性があります。この記事では、代表的な公的支援制度とその概要、申請方法、注意点について詳しくご紹介いたします。
代表的な公的補助制度
1. 国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費支給
亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬祭を執り行った人に対して「葬祭費」または「葬祭料」が支給されます。
- 支給額:一般的に5,000円〜70,000円(自治体によって異なる)
- 申請先:市区町村の役所・保険年金課
- 申請期限:葬儀から2年以内
- 必要書類:申請書、死亡診断書の写し、領収書、印鑑、通帳など
2. 健康保険(被用者保険)の埋葬料・埋葬費
会社員など健康保険(被用者保険)に加入していた方が亡くなった場合、健康保険組合や協会けんぽから「埋葬料」または「埋葬費」が支給されます。
- 支給額:5万円(全国健康保険協会の場合)
- 対象者:主に被扶養者・家族など
- 申請先:協会けんぽ・健康保険組合
- 必要書類:埋葬料請求書、死亡診断書、健康保険証、印鑑など
生活保護受給者の場合の「葬祭扶助」
生活保護を受けている世帯や、支払能力が著しく乏しい方の場合、葬祭扶助制度を利用することが可能です。
- 支給内容:直葬または簡易な葬儀に必要な最低限の費用を自治体が負担
- 対象者:生活保護受給世帯またはそれに準ずる事情のある方
- 申請先:福祉事務所・生活保護担当課
- 注意点:事前申請が必須。葬儀を先に行うと適用不可になる場合も
自治体独自の葬祭支援制度も存在
一部の自治体では、上記制度に加えて独自の補助制度を設けているところもあります。例えば、東京都葛飾区では収入に応じた補助金が、埼玉県の一部地域では葬儀社紹介と併せて割引制度が利用できる場合もあります。
詳細は各自治体の窓口やホームページで確認することが大切です。
公的補助を活用する際の注意点
- 申請期限に注意:原則、葬儀から2年以内。早めの手続きが安心
- 対象者・条件を確認:加入保険や生活状況に応じて利用可能な制度が異なる
- 実費をすべてカバーできるわけではない:補助はあくまで一部であることを理解しておく
まとめ
公的補助金・助成金は、遺族の経済的負担を少しでも軽減するために用意された大切な支援制度です。申請には手間もかかりますが、知らずに受け取れないままでは非常にもったいない制度でもあります。
特に、健康保険・国民健康保険・生活保護のいずれに該当するかで受けられる支援内容が異なるため、自身の状況に合った制度をしっかり確認しましょう。
大切な方を送り出す時間に、経済的な不安を少しでも減らせるよう、公的制度を賢く活用してまいりましょう。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
葬儀費用・金銭クラスター|費用相場から節約術まで完全ガイド