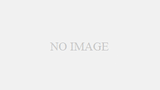葬儀の場は、故人を偲び遺族に哀悼の意を伝える神聖で厳粛な空間です。しかし、緊張や気まずさから何気なく発した言葉が、遺族や他の参列者を深く傷つけてしまうことも少なくありません。
「何を話せばいいかわからない」「沈黙が怖くてつい世間話をしてしまう」――そんな不安や迷いを持つ方のために、この記事では葬儀の場にふさわしい会話マナー、話してよい内容・避けるべき言葉についてわかりやすくまとめました。
話してよい言葉:遺族に対する思いやりを込めて
1. お悔やみの言葉
基本となるのは「このたびはご愁傷さまでございます」「心よりお悔やみ申し上げます」などの丁寧な弔意表現です。簡潔であるほど、相手にとっても負担にならず適切です。
2. 故人の思い出に触れる言葉
「いつも優しくしていただきました」「○○さんの笑顔が忘れられません」など、故人とのエピソードを軽く伝えるのは好印象です。ただし、話が長くなりすぎないよう注意しましょう。
3. 遺族への気遣い
「おつらい中、ありがとうございます」「どうぞご自愛ください」など、体調や心情への配慮を示す言葉も適しています。遺族の心に寄り添う姿勢が大切です。
避けるべき言葉:無意識に出やすいNG表現
1. 「おめでたい」言葉や忌み言葉
「浮かばれる」「繰り返す」「再び」「長生き」などは忌み言葉とされ、避けるべきです。また「お元気ですか」「よかったですね」といった通常のあいさつも、場にそぐわない場合があります。
2. 不謹慎な軽口やジョーク
気まずさを和らげようとして冗談を交えるのは厳禁です。葬儀は笑いの場ではなく、静かな哀悼の意を表す時間であることを忘れてはなりません。
3. 遺族への詮索や感情に踏み込む言葉
「どうして亡くなったの?」「いつから病気だったの?」「お金は大丈夫?」など、センシティブな質問は避けましょう。たとえ親しい間柄であっても、タイミングを選ぶべき内容です。
会話のトーン・声量にも注意
葬儀の場では声を張り上げたり、必要以上に感情的になるのはマナー違反とされます。静かに、落ち着いた声で、短く簡潔に話すことが望まれます。
また、周囲に他の参列者がいることを忘れず、私語は控えめに。葬儀中の会話は基本的に最小限にとどめ、必要があれば控室や式後に話すのがよいでしょう。
まとめ
葬儀における会話マナーは、ただ言葉を選ぶだけでなく、相手への思いやりと場の空気を読む力が試される場面です。言葉の選び方ひとつで、遺族の心に安らぎを与えることも、反対に不快感を与えてしまうこともあります。
話してよい内容・避けるべき表現を事前に知っておくことで、余計な心配なく故人への敬意を表すことができるでしょう。大切なのは、言葉の中に込められた「気持ち」なのです。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
マナー・服装・所作クラスター|葬儀参列の正しい立ち振る舞い