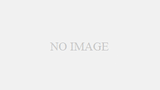大切な人が亡くなった直後、遺族が直面するのが様々な役所への手続きです。その中でも最も重要で最初に行う必要があるのが死亡届の提出です。
死亡届は、火葬や埋葬を行うための前提となる手続きであり、提出を怠ると火葬許可証が発行されず、葬儀自体が進められません。事務的な手続きであると同時に、法律上の義務でもあります。
本記事では、死亡届の基本的な出し方、必要書類、提出期限、そして注意点について、初めての方にもわかりやすくご紹介いたします。
死亡届とは?
死亡届は、人が亡くなったことを市区町村に届け出るための書類です。この届出を受理されることで、火葬や埋葬の許可が正式に下ります。
戸籍法に基づいて義務付けられており、提出を怠ると法的な罰則が課せられる場合もあるため、注意が必要です。
誰が提出するのか?
死亡届の届出義務者は、以下のように法律で定められています:
- 親族(配偶者、子、兄弟姉妹など)
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人
- 病院・施設の管理者(親族がいない場合)
実際には、喪主や親族が提出することがほとんどですが、葬儀社が代行する場合もあります。
死亡届の出し方
1. 死亡診断書の取得
病院で亡くなった場合は医師が、事故などであれば警察を通じて医師が死亡診断書(死体検案書)を発行します。
この死亡診断書と一体になっているのが「死亡届」用紙であり、この書類に必要事項を記入して提出します。
2. 必要書類の準備
- 死亡届(死亡診断書と一体)
- 届出人の認印(シャチハタ不可)
- 身分証明書(本人確認用)
3. 提出先
以下のいずれかの市区町村役場へ提出します:
- 死亡地
- 本籍地
- 届出人の住所地
提出後、火葬許可証と埋葬許可証が発行されます。これがなければ火葬はできません。
提出期限はいつまで?
死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。
ただし、国外で死亡した場合は3ヶ月以内となっており、在外公館(大使館・領事館)への提出が必要となるケースもあります。
提出のタイミングと注意点
- できる限り早めに:火葬や葬儀の日程に間に合うよう、1〜2日以内に提出するのが理想
- 24時間以内の火葬は不可:法律により、死亡確認から24時間以内の火葬は禁止されています
- コピーは不可:死亡届・診断書は原本のみ受理されます
死亡届と火葬許可証の関係
死亡届を提出すると、同時に火葬許可証が発行されます。この許可証がなければ、火葬場での火葬ができません。
火葬後は、火葬許可証に火葬済みの記載が加わり、埋葬許可証として墓地での納骨時に必要となります。
まとめ
死亡届は、葬儀や火葬、さらにはその後のさまざまな行政手続きの出発点となる、非常に重要な届け出です。故人を見送る際には感情的な負担も大きいものですが、手続きは期限内に正確に行うことが必要です。
葬儀社のサポートを受けつつ、事前に必要書類や提出先を確認しておくことで、スムーズな手続きを進めることができます。本記事を参考にして、安心して対応できるようご準備ください。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
葬儀後の手続きクラスター|相続・名義変更・行政手続きを網羅