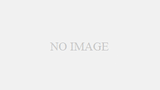仕事や距離の関係で葬儀に参列できないとき、故人やご遺族に対する哀悼の意を伝える手段として「弔電(ちょうでん)」があります。シンプルでありながらも、形式を守った言葉と気遣いを届けることができる弔電は、現代においてもなお大切な儀礼のひとつです。
しかし「いつまでに送ればよいのか」「どのような文章がふさわしいのか」と悩まれる方も少なくありません。今回は、弔電を送るタイミングや基本マナー、さらには具体的な文例を通して、誰でも安心して利用できるよう詳しく解説いたします。
弔電とは?
弔電とは、葬儀・通夜の際に、参列できない人が哀悼の意を電報で伝える手段です。NTTや民間の電報サービスを通じて、葬儀会場や喪主のもとに届けられます。
現代ではスマートフォンやメールが主流になりつつあるものの、弔電はあくまで「公式な弔意表現」として格式を持ち、受け取る側にとっても重みのある気遣いとなります。
弔電を送るタイミング
最も理想的なタイミングは「通夜または葬儀の当日午前中」に届くように手配することです。遅くとも葬儀開始の1~2時間前までには到着するよう心がけましょう。
突然の訃報で間に合わない場合でも、通夜が行われる場合はその時間に合わせて手配すれば問題ありません。故人の住所ではなく、通夜・葬儀が行われる「会場宛て」に送ることが基本です。
弔電のマナーと注意点
1. 宛先の記載
宛名は「○○家 ご遺族様」または「喪主 ○○○○様」とします。個人名を記載する場合は敬称を忘れずに。
2. 使用する言葉
弔電では忌み言葉や過度な感情表現は避け、簡潔で丁寧な言葉を心がけましょう。宗教・宗派により異なる場合もあるため、事前に確認できるとより安心です。
3. 句読点を使わない
電報では句読点(「。」「、」)は使用しないのが通例です。読みやすく整った改行を意識することが大切です。
弔電の文例
一般的な弔電文例
このたびはご逝去の報に接し謹んでお悔やみ申し上げます
ご冥福を心よりお祈りいたします
故人と親しかった場合
在りし日のお姿を偲び心より哀悼の意を表します
心安らかにお眠りになられますようお祈り申し上げます
ビジネス関係の場合
ご尊父様のご逝去に際し謹んでお悔やみ申し上げます
心よりご冥福をお祈り申し上げます
遺族への配慮を込めた文例
ご家族の皆様のお悲しみをお察しいたします
どうかご自愛くださいますようお祈り申し上げます
弔電の申し込み方法
NTTの「115」や、インターネットの弔電サービス(VERY CARD、でんぽっぽなど)から簡単に申し込むことができます。台紙や文面を自由に選べるサービスもあり、故人の雰囲気に合った演出が可能です。
急ぎの場合は電話での申し込みが最も迅速ですが、ネットなら深夜でも対応できるため状況に応じて使い分けましょう。
まとめ
弔電は、直接会場に足を運べないときでも、丁寧に弔意を伝えられる大切な手段です。送るタイミングや文面に少し気を配るだけで、遺族の心に温かく届くことでしょう。
形式的に見えても、そこにこめた想いはしっかり伝わります。故人を偲ぶ気持ちと遺族への配慮を大切にしながら、正しいマナーで弔電を送りましょう。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
マナー・服装・所作クラスター|葬儀参列の正しい立ち振る舞い