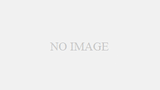企業のトップや役員、創業者などが亡くなった際に執り行われる「社葬(しゃそう)」。テレビや新聞で「○○氏の社葬が行われた」という報道を目にしたことがある方も多いでしょう。
しかし、実際の社葬がどのように進行されるのか、また一般的な「個人葬(こじんそう)」とどこが違うのか、明確に理解している方は多くありません。
本記事では、社葬の基本的な流れと個人葬との違いについて、企業側・参列者側の両視点からわかりやすく解説してまいります。
社葬とは?
社葬とは、企業が主催して行う葬儀のことです。通常、企業の創業者や取締役、功労者などが亡くなった場合、その功績を称える目的で開催されます。
企業イメージにも関わるため、規模が大きく、形式的にも厳粛で組織的な進行が求められるのが特徴です。従業員はもちろん、取引先、株主、行政関係者なども招かれることが一般的です。
社葬の主な流れ
- 社内での開催決定と準備
取締役会などで社葬の実施を決定し、葬儀社・会場・日程などを調整します。社内に「社葬委員会」を設けることもあります。 - 葬儀形式の選定
仏式・神式・無宗教式など、故人や企業方針に合わせて選定します。 - 案内状・告知の発送
取引先や関係者に案内状を送付。新聞に訃報広告を出す場合もあります。 - 社葬当日の進行
開式→読経・弔辞・焼香→喪主または代表挨拶→閉式→会食(任意)といった流れが基本です。 - 後日処理
香典の管理、返礼品の送付、社内報告などの事後対応も重要です。
個人葬との違い
| 項目 | 社葬 | 個人葬 |
|---|---|---|
| 主催者 | 企業(社葬委員会など) | 遺族・親族 |
| 対象者 | 創業者・役員・功労者 | 一般の個人 |
| 参列者 | 社員・取引先・関係各所 | 親族・友人・地域住民 |
| 規模・費用 | 大規模・企業負担 | 比較的小規模・遺族負担 |
| 目的 | 功績への敬意・企業広報の一環 | 故人との私的な別れ |
社葬の特徴と留意点
企業イメージとの連動
社葬は企業の対外的な「顔」としての役割も担うため、演出や挨拶、進行などに細心の配慮が求められます。内輪の雰囲気は避け、儀式としての厳粛さを保つことが重要です。
社員への周知と対応
社員には弔意を表す場として、参列のマナーや受付当番などの役割が割り当てられる場合もあります。社葬の目的や意味を社内で周知しておくことが望まれます。
香典の扱い
社葬では香典を辞退するケースも多く、案内状に「ご香典・ご供花の儀はご遠慮申し上げます」と明記することも一般的です。
社葬と合同葬の違い
「合同葬」は、社葬と個人葬を同時に行う形式です。企業と遺族が協力し、それぞれの意向を反映させて進めます。社葬よりも私的な雰囲気が残る一方、企業の意向もしっかり組み込まれるため、バランス感覚が求められます。
まとめ
社葬は企業にとっての重要な儀式であり、単なる葬儀ではなく「社会的なメッセージ」を内包する場でもあります。個人葬との違いを正しく理解し、関係者として適切なマナーで対応することが大切です。
また、遺族の気持ちにも配慮しながら進行を円滑に保つことで、故人への敬意と企業としての誠意の両方を伝えることができるでしょう。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
葬儀の種類・宗教クラスター|形式・宗教ごとの特徴を解説