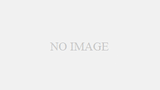日本の葬儀で最も一般的な形式である仏式葬儀には、独特な儀礼や用語が数多く存在します。参列する側にとっても、遺族として葬儀を執り行う場合でも、聞き慣れない言葉に戸惑うことは少なくありません。
この記事では、仏式葬儀で頻出する代表的な用語をピックアップし、それぞれの意味と使われる場面、知っておくべきマナーを解説します。葬儀に臨むうえでの理解が深まり、安心して儀式に参加するための一助となれば幸いです。
戒名(かいみょう)
戒名とは、故人が仏門に入った証として僧侶から授けられる名前です。生前の名前ではなく、死後に仏教的な意味を持つ名を授かることで、成仏への導きとされます。
- 構成:院号・道号・戒名・位号 など(宗派により異なる)
- ランクが存在:戒名には階級があり、院号付きは高額になることも
- 費用相場:約10万円〜50万円(内容により上下)
戒名は葬儀・法要・位牌・墓石に記され、仏式の葬送において欠かせない存在です。
お布施(おふせ)
お布施は、僧侶への謝礼として渡す金銭で、読経や戒名授与、法要などの仏事を依頼した際にお渡しします。厳密には「対価」ではなく、あくまで感謝と供養の気持ちとしての贈り物です。
- 金額の目安:葬儀一式で20万円〜50万円程度が相場
- 包み方:白封筒または奉書紙で「お布施」と表書きし、内袋に金額と施主名を記載
- お車代・御膳料:別途用意することも多く、それぞれ5千円〜1万円が相場
お布施は宗派や地域、寺院との関係性によっても変動しますので、事前に確認することが大切です。
初七日(しょなのか)
初七日は、故人が亡くなってから七日目にあたる日で、仏教における「忌日法要(きにちほうよう)」のひとつです。亡くなった日を含めて7日目に、初めての追善供養を行うとされます。
- 現在の主流:火葬当日に「繰り上げ初七日」として同日に執り行うケースが多い
- 内容:僧侶による読経、遺族による焼香、お布施の用意など
- 意味:故人の魂が極楽浄土へ向かう過程を支えるための祈り
初七日はその後の四十九日法要までの起点にもなります。
その他よく使われる仏式用語
- 通夜:故人との最後の夜を過ごす儀式。仏式では読経と焼香が行われる
- 精進落とし:葬儀後の会食。故人を偲び、僧侶や参列者への感謝を込めて行う
- 中陰(ちゅういん):死後49日間のこと。魂が来世へ旅立つ準備期間
- 四十九日(しじゅうくにち):中陰の最終日で、納骨や法要が行われる
まとめ
仏式葬儀では、宗教的な意味を持つ専門用語が多く登場しますが、それぞれに故人を想う深い意義が込められています。戒名・お布施・初七日など、よく使われる言葉の意味を理解することで、葬儀の流れがよりスムーズになり、遺族としても参列者としても心を込めて向き合えるはずです。
慣れない言葉に戸惑った際には、遠慮なく葬儀社や僧侶に確認しながら、失礼のないよう丁寧な対応を心がけてまいりましょう。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
葬儀の種類・宗教クラスター|形式・宗教ごとの特徴を解説